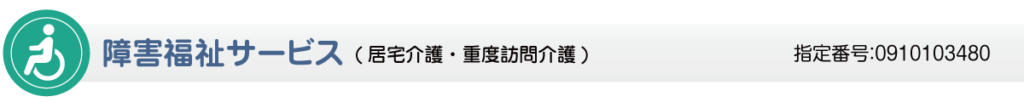

重度訪問介護のサービス
訪問介護のサービス内容
重度訪問介護は、重度の肢体不自由や知的障害、精神障害により、常に介護を必要とする方が、住み慣れたご自宅で自立した生活を続けられるように支援する障害福祉サービスです。この記事では、その具体的なサービス内容から利用対象者、手続き、費用まで、詳しく解説します。


重度訪問介護とは?
重度訪問介護は、障害者総合支援法に基づき提供されるサービスの一つです。単に身体的な介護を行うだけでなく、調理や洗濯などの家事、外出時の付き添い、コミュニケーションの支援、緊急時の対応や見守りまで、利用者の生活全般にわたって長時間、総合的な支援を行うのが大きな特徴です。これにより、重度の障害がある方でも、施設に入所するのではなく、地域社会の一員として自宅で暮らし続けることが可能になります。
1.
対象となる方
障害支援区分が4以上であること
以下のいずれかの条件を満たすこと
肢体不自由者の場合:二肢以上に麻痺などがある。
障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されている
知的障害者・精神障害者の場合:障害支援区分の認定調査項目のうち、行動関連項目(12項目)の合計点数が10点以上である。
具体的には、筋萎縮性側索硬化症(ALS)や筋ジストロフィーなどの難病の方、脊髄損傷による四肢麻痺の方、重度の知的障害や精神障害により行動上著しい困難がある方などが利用しています。

2.
対象となる方
| サービスの種類 | 具体的な内容例 |
| 身体介護 | 食事、入浴、排泄、着替えの介助、体位交換、服薬介助、たんの吸引や経管栄養などの医療的ケア(※研修を受けた介護職員が実施) |
| 家事援助 | 調理、洗濯、掃除、生活必需品の買い物、薬の受け取りなど |
| 移動支援 | 通院、官公庁での手続き、余暇活動(散歩、買い物、イベント参加など)のための外出時の付き添い |
| 見守り・その他 | 利用者の心身の状況に応じた見守り、コミュニケーション支援、緊急時の対応、その他日常生活を送る上で必要な援助 |

3.ご利用開始までの流れ
重度訪問介護を利用するためには、お住まいの市区町村への申請手続きが必要です。
相談・申請
お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口や、相談支援事業所に相談します。
利用申請
市区町村の窓口で、障害福祉サービスの利用申請を行います。
認定調査
認定調査員が自宅などを訪問し、心身の状況について聞き取り調査を行います。また、主治医から意見書を取り寄せます。
障害支援区分の認定
認定調査の結果と主治医の意見書をもとに審査会が開かれ、障害支援区分が決定されます。
サービス等利用計画案の作成
指定特定相談支援事業所の相談支援専門員と一緒に、どのようなサービスをどのくらい利用したいかという「サービス等利用計画案」を作成します。
(自治体や状況によってセルフプランでも可能な場合があります)
支給決定・受給者証の交付
提出された計画案などに基づき、市区町村がサービスの支給量などを決定し、「障害福祉サービス受給者証」が交付されます。
事業者との契約・利用開始
サービスを提供している事業者の中から利用したい事業所を選び、契約を結ぶと、サービスの利用が開始されます。
4.重度訪問介護のメリット・デメリット

メリット
住み慣れた自宅での生活継続: 施設に入所せず、自分らしい生活を送ることができます。
24時間365日の安心: 必要に応じて長時間の支援が受けられるため、利用者本人も家族も安心して生活できます。
社会参加の促進: 外出支援により、趣味の活動やイベント参加など、社会とのつながりを維持・拡大できます。
家族の介護負担軽減: 専門的な支援が入ることで、家族の身体的・精神的な負担が大幅に軽減されます。

デメリット・注意点
事業所探し: 特に24時間対応など、重度な支援に対応できる事業所が地域によっては少ない場合があります。
ヘルパーとの相性: 長時間にわたり密な関わりを持つため、ヘルパーとの相性が非常に重要になります。事業者とよく相談し、必要であれば担当者の変更を依頼することも考えましょう。
制度の理解: 利用できるサービスの範囲(例:本人以外の家族のための家事は不可など)について、利用者・家族・事業者の三者で正しく理解しておくことが、円滑なサービス利用につながります。
重度訪問介護は、重い障害を持つ方々が地域でその人らしく生きるための非常に重要なサービスです。利用を検討されている方は、まずはお近くの相談窓口に問い合わせてみてください。
緊急時の対応: 夜間や休日など、緊急時の連絡体制や対応について確認しておくと安心です。
複数の事業所を比較する: ケアマネジャーに複数の事業所を紹介してもらい、それぞれの説明を聞いて比較検討することをおすすめします。
訪問介護は、高齢者が尊厳を保ちながら自分らしい生活を続けるための心強い味方です。この情報が、あなたやあなたの大切なご家族にとって、より良い在宅介護を実現するための一助となれば幸いです。
