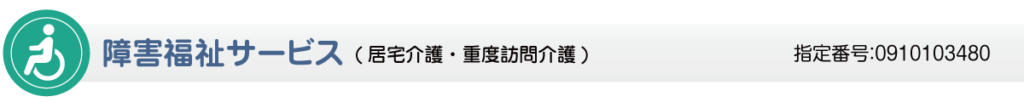

居宅介護のサービス
居宅介護のサービス内容
居宅介護(きょたくかいご)とは、障害をお持ちの方(身体・知的・精神・難病など)が、自宅で安心して暮らせるよう、訪問介護員(ヘルパー)が自宅を訪問して日常生活をサポートするサービスです。


居宅介護とは?
居宅介護サービスは、障害のある方が地域で自立した生活を送るために、自宅で日常生活の支援を受けられる障害福祉サービスの一つです。サービス内容には、入浴・排泄・食事などの身体介護、調理・掃除・洗濯・買い物などの家事援助、外出時の移動支援が含まれます。利用者の状態や希望に応じて支援内容を柔軟に調整し、生活の質の向上と家族の介護負担の軽減を図ることを目的としています。
1.
対象となる方
以下のいずれかに該当する方が対象です:
年齢要件:原則18歳以上(児童は「居宅介護」ではなく「居宅介護に準じたサービス」が該当)
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳などを所持している方
難病等で、障害者手帳がなくても市町村が必要と認めた方

2.
サービス内容
■ 身体介護(生活援助)
利用者の身体に直接触れて行う支援:
- 入浴・清拭・洗髪
- 排泄の介助(トイレ誘導、おむつ交換など)
- 食事介助
- 更衣や整容の介助
- 体位変換、移乗介助 など
■ 家事援助(生活援助)
日常生活を支えるための間接的な支援:
- 調理、掃除、洗濯
- 買い物代行
- 衣類の整理
※原則として、利用者本人のための家事のみ
■ 通院等介助
医療機関への通院に付き添う支援:
- 自宅から病院までの移動
- 院内での付き添い
※通勤・通学など医療以外の外出には使えません。
必要に応じて市区町村が認める範囲でのサービスがあります

ご利用開始までの流れ
重度訪問介護を利用するためには、お住まいの市区町村への申請手続きが必要です。
相談・申請
お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口や、相談支援事業所に相談します。
サービス等利用計画案の作成
「サービス等利用計画(ケアプラン)」の作成が必要です。サービス等利用計画案は、障害福祉サービスを利用する際に必要な計画書で、利用者の希望や課題に基づき、どのような支援が必要かを明確にします。相談支援専門員が本人や家族と面談しながら作成し、サービスの種類や頻度などを具体的に記載します。
障害支援区分の認定
障害支援区分の認定調査は、市区町村が障害者の心身の状況や生活の困難さを評価し、必要な支援の量を判断するために行います。調査員が聞き取り調査を行い、その結果をもとに一次判定・審査会を経て、区分1~6に認定されます。
支給決定・受給者証の交付
市区町村は、障害支援区分やサービス等利用計画案をもとに、必要なサービスの種類や量を審査し、支給決定を行います。決定後、「障害福祉サービス受給者証」が交付され、そこには利用できるサービス内容や支給量、自己負担上限額、有効期間などが記載されています。この証があって初めてサービスの利用が可能になります。
事業者との契約・利用開始
受給者証の交付後、利用者は市区町村が指定する介護サービス事業所と契約を結びます。契約では、提供するサービスの内容や回数、訪問時間、担当ヘルパーなどを具体的に決め、「個別支援計画書」を作成します。利用者の希望や生活状況に合わせた支援が提供されるよう、事業所と十分に話し合って契約を進めることが大切です。
併用できるサービス
居宅介護サービスと併用できる主なサービスには、利用者の状態や支援の必要性に応じて「重度訪問介護」「同行援護」「行動援護」などがあります。たとえば、常時介護が必要な重度の障害者には「重度訪問介護」が適用され、長時間の見守りや外出支援が可能です。視覚障害者には移動時の安全確保や情報支援を行う「同行援護」、知的・精神障害で行動に著しい困難がある場合には「行動援護」があります。これらのサービスは状況に応じて柔軟に組み合わせて利用できます。
